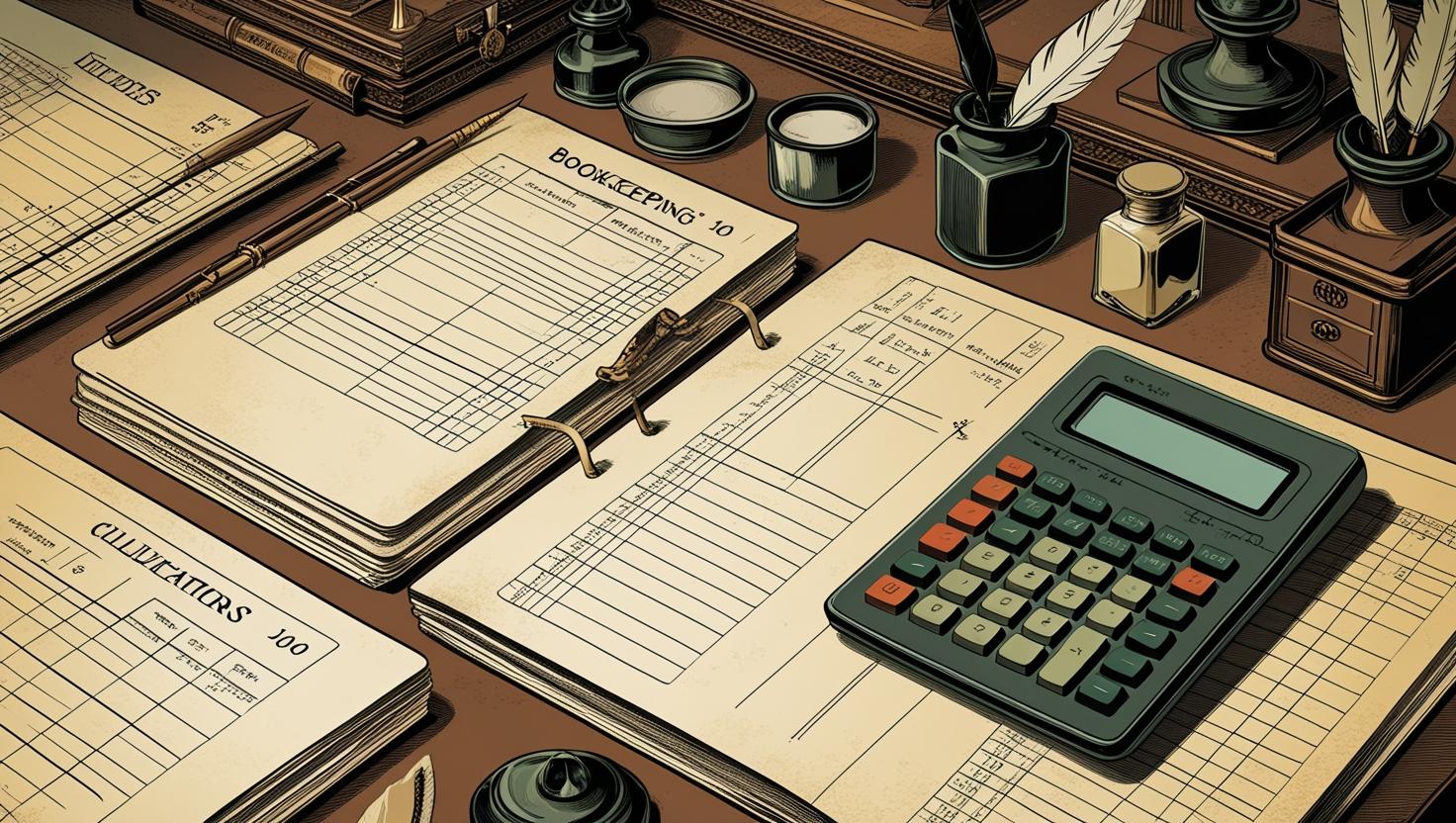前回の記事で、借方と貸方の位置は分かりましたね。
ここから、本格的に簿記の内容に入っていきます。

ぺむ
そもそもさ、この勘定科目は
借方・貸方どっちなんさ?
ニッシー
この記事では、どの勘定科目をどちらに振り分けるのかについて、筆者の覚え方をもとに説明していきます。
この記事では、独学で日商簿記検定2級に合格した筆者が、
経理の実務に役立つ簿記知識を解説します。
尚、本ブログは実務に役立つ、簿記検定3級相当の基礎的な内容を取り扱っています。
検定合格を目指して、より本格的に学びたい方は
通信講座などもおススメします。
勘定科目は5グループ!
勘定科目というのは、基本的に、資産・負債・純資産,費用・収益の5つのグループのどれかに属しています。
そして、それぞれのグループごとに、増減によって、借方と貸方どちらに記載するというのかは、ルールとして決まっているんですね。
下図をご覧下さい。この図がスッと頭に入るのならば、正直今回の記事を読む必要はありません笑
【図作成予定】

ぺむ
難しくて、覚えられないよ…
そう。初学者にはちょっと難しいのです。
ちなみに、筆者も簿記2級に合格した当時、よく理解していませんでした。
この記事では、表を覚えなくても分かる考え方を紹介していきます。
【本題】嬉しいときは借方!悲しいときは貸方!
嬉しい時は借方、悲しい時は貸方理論を提唱します!
これは、筆者が検定試験を勉強の際に、使っていた覚え方です。

ぺむ
どういうこと…??
いきなりの、独自理論に困惑しちゃいました?笑
それでは具体例を用いて解説していきますね。
【事例】
ぺむは、100円の商品を仕入れ、現金で支払った。
さあ、どのように考えればいいでしょうか。
この取引では、仕入と現金いう勘定科目を使います
表を使うと?
仕入れは資産のグループに属しています。
資産の増加は借方です。
また、現金も資産のグループですが、資産の減少は貸方でしたね。
よって、次のようになります。
(借方)仕入100/(貸方)現金100
表を覚えてないと難しくないですか?
そこで、嬉しい時は借方・悲しい時は貸方理論を使うのです!
理論ならどう?
ニッシー
仕入れると、商品が手元に増えて、嬉しいですよね!

仕入を、か・り〰️
ニッシー
でも、お金を支払ったので、手元の現金は減ってしまいました…
悲しい…

現金を、か・し〰️
どうです?
(借方)仕入/(貸方)現金というのがすぐイメージできたでしょう?
次回以降、この理論を用いて3級で扱う勘定科目について
それぞれみていきましょう。
まとめ
嬉しい時は借方、悲しい時は貸方理論を解説しました。
筆者的には、この考え方で、だいたいの取引に対応できると思っているのですが、この考え方がわかりやすかったという方は、ぜひ参考にしてみて下さいね!
次回、勘定科目編にご期待下さい。
日商簿記検定2級は独学でも充分に合格できます。
筆者が実際に使用していた書籍の出版社から販売されている
最新の市販テキスト・問題集を記載しておくので
この記事を読んで簿記検定に興味が出てきた方は、
ぜひ手に取ってみてくださいね。